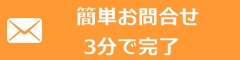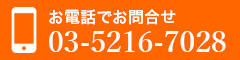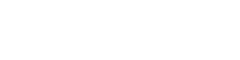当事務所では,平成29年12月18日のホームページ開設以来,弁護士費用(報酬基準)について初めての全面改定を実施しました(近日施行予定)。
全面改定後の弁護士費用(報酬基準)の詳細については,施行日近くなりましたら公開いたしますが,概要については,トップページ「弁護士選びのポイントは「誠実さ」!」から「弁護士報酬基準の全面改定(近日施行予定)」のページをクリックしてご覧ください。そのほか,弁護士費用(報酬基準)全面改定の経緯又は趣旨,当事務所の弁護士費用(報酬基準)に対する基本的な考え方(当事務所が考える弁護士費用の「適正価格」など)の詳細については,トップページ「弁護士選びのポイントは「誠実さ」!」から各ページをクリックしてご覧ください。
以下は,全面改定前の弁護士費用(報酬基準)です(順次改定中。近日中に全面改定する予定です)。
1.法律相談(リーガル・カウンセリングと無料診断,継続相談)
「リーガル・カウンセリング」あるいは「無料診断」までのお問合せ・ご相談については,一切相談料はかかりません
当事務所では,皆様から電話又はメールでお問合せがあった場合,事件を受任するか否かにかかわらず,すべての案件について「リーガル・カウンセリング」あるいは「無料診断」を実施しています。
2.顧問契約とホームロイヤー(かかりつけ弁護士)登録制度
顧問契約3.3万円~ / ホームロイヤー登録料5.5万円のみ
当事務所では,主に法人向けの顧問契約のほか,一般個人の方々がお気軽に弁護士を利用できるように,ホームロイヤー(かかりつけ弁護士)登録制度を実施しています。
3.一般民事事件(基本的な報酬基準)
経済的利益の額×8%~
民事事件(訴訟事件)の着手金・報酬は,「経済的利益の額」を基準として算定します。
4.お問合せの多い主な事件類型
① 刑事事件(起訴前,起訴後・公判)
受任前の接見 1.1万円 / 起訴前 22万円 / 起訴後33万円
② 少年事件(家裁送致前,家裁送致後・審判)
家裁送致前 22万円 / 家裁送致後 33万円
③ 外国人・入管事件(仮放免,在留特別許可,退去強制命令取消訴訟,再審情願)
面談 1.1万円 / 仮放免許可申請 7.7万円
④ 債務整理(過払金返還請求,任意整理,自己破産,個人再生)
任意整理 1社当たり2.2万円
⑤ 離婚(離婚の協議・調停・訴訟/婚姻費用,親権・養育費,財産分与・慰謝料請求,年金分割)
離婚協議 22万円
⑥ 相続(遺言,遺留分,遺産分割,相続放棄,限定承認)
遺言書作成 22万円~55万円
⑦ 労働事件(残業代・退職金等請求,不当解雇など地位確認請求,過労死など労働災害)
一般民事事件の基準に従う
⑧ 交通事故(被害者側)
一般民事事件の基準に従う
5.本人調停(訴訟)支援制度
準備中です。2018年10月4日のコラム「本人調停の勧め(離婚や遺産分割は自力で対応できる!)」をご覧ください。